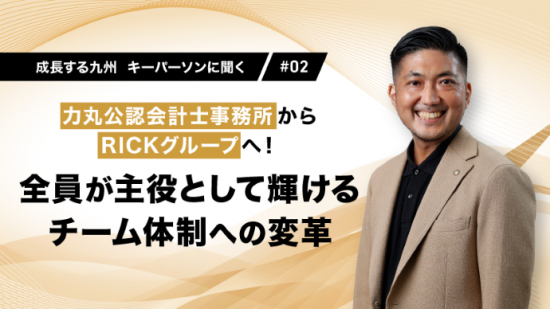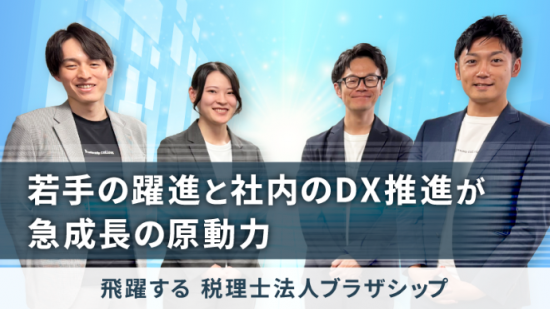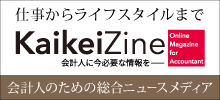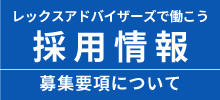転職お役立ち情報

公認会計士は会計のスペシャリストで、社会的な信頼があり、高い報酬も約束された職業です。
そんな公認会計士には組織に属する働き方だけでなく、独立開業やフリーランスへの転身などさまざまな選択肢があります。
特に「高年収を得たい」「好きな仕事を自由に受けたい」等の理由から、独立開業を目指す公認会計士は多くみられます。
実際のところ、独立開業した公認会計士の平均年収は、公認会計士全体の平均年収よりも高めの水準です。
しかし、必ずしも高年収を得られるとは限りません。
また、独立開業にはメリットだけでなく注意するべきデメリットも多く存在します。
今回は公認会計士の独立開業で失敗しないために知っておくべき情報を紹介します。
公認会計士の独立・開業というキャリアパスについて
前提として、本記事では「独立開業」という言葉を、個人の会計士事務所を興すという意味で用いています。
組織に属さずフリーランスとして活動する公認会計士は含めない点にご注意ください。
その上で、独立・開業とフリーランスへの転身、それぞれの特徴を紹介します。
独立・開業の特徴は以下の通りです。
- 継続案件や規模の大きい案件が中心になりやすい
- 税理士登録をして税務業務も請け負うことが多い
- フリーランスに比べて仕事量が安定しやすい傾向
- 事務所の運営業務(本業とは異なる業務)が多く発生するため手間がかかる
続いてフリーランスの特徴を紹介します。
- 単発案件を数多く受けるケースが多い
- 事務所を興す場合よりも仕事の幅が広くなりやすい
(監査、執筆活動、講師活動の全てをこなす等) - 働き方の柔軟性が高い
- 社会的信用の得やすさや安定性は独立開業に比べて低めの傾向
どちらが良いと一概にはいえませんが、独立開業の方が安定した働き方をしやすいでしょう。
公認会計士の独立開業後の仕事内容
公認会計士試験に合格すると、多くの人は監査法人に入所し、修了考査合格に向けて実務経験を積みます。
そのまま、監査法人に残り、パートナーを目指す人もいますが、大手監査法人でパートナーまで上り詰めるのは相当狭き門です。
そこで、修了考査に合格し、正式に公認会計士と名乗れるようになると、M&Aアドバイザリー業務など、監査以外の経験も積むために監査法人から出る人も出てきます。
FASと呼ばれるコンサルティングファーム、事業会社の経理や経営企画、税理士登録をして税理士法人や会計事務所に転職をします。
その次のステップとして独立を選択する会計士が多くいます。
どのような業務で独立開業するのでしょうか。
公認会計士の将来性についてはこちらの記事もご覧ください。
公認会計士の独立:税務業務中心の会計事務所
公認会計士が独立開業する場合、税理士登録をし、税務業務を柱とすることが多いです。
一定数のクライアントが獲得できれば、毎月の顧問料が定期的に入るので、事務所の経営が安定するというメリットがあるからです。
しかし公認会計士の独占業務は監査で、監査法人でキャリアを積むだけでは税務の知識では税理士には敵いません。
そこで、大手税理士法人や会計事務所で経験を積み、税務業務を身につけてから、独立を目指すという方法を選択するケースが多いです。
公認会計士の独立:財務・会計コンサルティング業務
公認会計士として独立後、財務・会計分野を中心としたコンサルティング業務を行う場合には、監査法人時代に培った知識と経験も活かすことができます。
財務諸表作成や分析のサポート、資金調達の方法や財務分野での経営戦略のアドバイス等、
公認会計士として得意とする分野のサービスを提供することになります。
公認会計士の独立:M&A、IPO中心のコンサルティング業務
公認会計士が独立後にコンサル業務を行う場合、M&Aなどの企業の買収・合併、組織再編に関わるファイナンシャル・アドバイザリーとして活躍することも考えられます。
この場合にはFASなどで培った、デューデリジェンスやバリュエーションの知識が役立つでしょう。
公認会計士の独立:経営コンサルティング業務
経営戦略策定を積極的にサポートする、経営全般に対するコンサル業務を展開することもできます。
しかし、経営戦略に関わるアドバイスまで行うには、公認会計士としての知識のみに留まらない、幅広く深い知識と経験が必要です。
会計士としての監査や内部統制の視点、税理士としての業務経験、その他の各コンサルティングの経験を総合的に活かすことができるでしょう。
公認会計士の独立:監査法人での非常勤業務
公認会計士として独立開業する場合、最初はクライアントを獲得するのに苦労する場合があります。
そのようなときは、監査法人で非常勤で副業をする会計士も多くいます。
また、報酬の確保という面だけではなく、個人では難しい監査という会計士の独占業務に常に携わりたいと希望する人もいます。
この場合の日当は3万円~5万円前後と言われています。
監査業務は繁忙期と閑散期がはっきりとしており、繁忙期はとにかく人手がほしいので、OBの非常勤勤務を歓迎する法人も多いので、チェックすると良いでしょう。
”業務委託”での働き方も注目されています。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
公認会計士の独立:会計専門学校での講師
更に、会計士を目指す専門学校などや実務補習所などで講師を務める人もいます。
教え方が上手い、生徒からの評判が良いなど、実績を高く評価されれば、報酬も高くなります。
知識だけでなく実際の経験を話すことで、後輩たちが良い会計士になる手助けをしていきましょう。
公認会計士の独立:金融機関等のセミナーの講師
金融機関などが行う、顧客向けのセミナーの講師をする場合や、自社の従業員向けの社員教育の一環として、公認会計士が講師を引受けることがあります。
独立開業後は人脈が重要となります。
こういったセミナー講師は人脈からの依頼が多く、引き受けていくことでさらに人脈が広がり、もっと大きな案件やクライアントの受注となる場合もあります。
先に述べた専門学校の講師やセミナー講師を担当したことが書籍の執筆につながることもありますので、ご自身の可能性をどんどん広げていってください。
ご転職者インタビュー
独立した公認会計士のリアルな年収
独立した公認会計士の年収は、平均して1,000万円ほどといわれています。
公認会計士全体の平均年収900万円~1,000万円と比較すると、より高年収を得られる可能性があるといえるでしょう。
ただし、年収は仕事量や単価によって異なるため一概にはいえません。
たとえば非常勤の監査業務の時給は4,000円から1万円と幅が広く、日給ベースで考えればさらに差が広がります。
仕事の難易度やクライアントとの単価交渉の結果によっても報酬は大きく変動します。
先述のように、独立した公認会計士の平均年収は1,000万円がひとつの目安です。
ただし年収の幅は300万円~3,000万円ともいわれており、明確な平均年収を判断するのは難しいのが事実です。
高年収を得られる可能性があるとはいえ、実際にどれほどの年収になるかは人によって全く異なるといえるでしょう。
公認会計士が独立をするために必要な準備
クライアントとの信頼関係を作ること
監査法人時代や転職後の会計事務所やコンサルティングファームで、クライアントとの強い信頼関係を築いておくことは大切です。
独立した後、案件を紹介して貰ったり、公認会計士を探している新しいクライアントを紹介してもらえれば、仕事の幅が広がります。
特に、大手監査法人では、担当するクライアントは日本を代表する大手企業が揃っていますし、その経営者クラスの方々と対等に接する機会に恵まれているので、その方たちから信頼を得られることは、独立に向けて大きな強みとなるでしょう。
独立に必要なスキルを身につける
監査法人の業務はやはり監査業務がほとんどです。
M&Aアドバイザリー業務などは、監査法人から分社化されたFASと呼ばれる別法人が行うのが主流となっています。
その他、内部統制アドバイザリーやIPOサポートなどがありますが、人気があるため、異動して経験を積むことは簡単ではりません。
ですから、監査法人に長年勤めただけでは、アドバイザリー業務等の経験を積むのが難しくなっています。
監査業務を主としながら、スポットで担当することはできますので、監査以外の業務に積極的にチャレンジするようにしましょう。
しかしそこで身につける、デューデリジェンス、バリュエーションなどの知識は、公認会計士であればあって当然の知識ですので、それだけで強みになるわけではありません。
独立後の自分の方向性をイメージした時、他の公認会計士にない自分の強みは何かについて、自分の得意分野や能力の棚卸し作業をすることが有効かと思います。
監査法人内での人脈を作っておく
監査法人時代に監査法人内でしっかりと人脈を作っておく事は、独立を考えているなら、とても重要です。
非常勤の仕事を紹介して貰う可能性や、監査法人では引き受けない案件を紹介してもらえる可能性があり、公認会計士として独立後の仕事の幅が広がります。
また、逆に、個人の事務所では対応できない大きな案件が生じた場合にも、紹介できる監査法人の人脈を持っていることは、その会計士の信用力を高めるでしょう。
税務業務を担当できるよう税理士登録を済ませておく
公認会計士として独立開業するのであれば、事前に税理士登録を済ませておきましょう。
「公認会計士の独立開業後の仕事内容」でも触れたように、独立開業する公認会計士は税務業務を軸とするケースが多いです。
個人が運営する小規模な会計士事務所では、個人や中小企業等からの依頼が中心となります。
個人や中小企業等は監査および高度な会計業務はあまり必要としません。
それ以上に、より身近である税務関連の方が重要性が高いケースが多くみられます。
公認会計士資格の保有者は税理士試験に合格する必要なく、申請すれば税理士登録が可能です。
必要書類の用意や手続きなど申請には手間がかかるものの、税務サービスを提供できるようになるメリットは非常に大きいです。
そのため、独立するのであれば税理士登録は済ませるべきといえます。
公認会計士が独立・開業するメリットは?
クライアントから感謝される満足感
監査法人での監査業務は、クライアントの作成する財務諸表の適正性を保証するという、クライアントの利益に繋がる業務ではありました。
しかし、その業務の内容は、財務諸表の不正や誤謬を見抜く必要から、どうしても批判的な機能が強くなってしまいます。
経理担当者にとっては、監査が入るということは、あまり歓迎される事ではないのが実情です。
一方、アドバイザリー業務などは、批判的機能よりも、クライアント側の立場に立ってアドバイス機能を発揮出来ます。
公認会計士として独立後、クライアントからは、敬遠されるよりも頼りにされ、感謝される機会が増えることとなり、やりがいを感じることが出来るでしょう。
様々なことにチャレンジし自分の世界を広げる
監査法人では、様々な企業を担当することで、普段は見られない企業の内部を見る機会があり、経験が積めます。
しかし、監査業務は定型業務が主になりますので、一定の経験を積んだ後は、公認会計士としての知識を活かして、もっと幅広い業務にチャレンジしたくなる方が多いようです。
FASなどで経験を積み、更に自分の力を試してみたいという場合は、公認会計士として独立し、自分の世界を広げる選択肢もあります。
高収入のチャンス
独立後の収入については、各自の営業努力や方向性によって大きな差があるので一概には言えません。
監査法人時代より下がる方もいるでしょうし、成功すれば数千万稼ぐ会計士もいるでしょう。
公認会計士として独立を考えるなら、独立前から準備をし、自分の強みを活かすことで、高収入を狙えるチャンスは高まると考えられます。
公認会計士の年収についてはこちらの記事もご覧ください。
公認会計士が独立・開業するデメリットは?
メリットがあれば、デメリットもあります。
公認会計士が独立した時のデメリットとは何でしょう?
安定した収入がなくなる
大手の監査法人や会計事務所、コンサルティングファームを退職すれば、それまでの安定した高収入を手放す事になります。
独立直後はクライアントが少なく、どうしても安定的な収入を得ることはできません。
しかし、自分の努力次第では、数千万の年収を得ることも可能ですから、実力次第となります。
大手の事務所のような大規模な案件は受注できなくなる
個人の事務所で受注できる案件は、大手事務所で手掛けていたものに比べれば、規模が小さくなります。
それに伴い、様々な案件に触れることでスキルアップ出来る可能性も減る事になるので、より積極的にスキルアップに心がけることが必要になるでしょう。
監査法人に勤務しているという肩書きがなくなる
公認会計士試験合格後は、大多数の人が大手監査法人に勤務すると考えられます。
監査法人に就職すると、入所したばかりの新人でも、クライアントからは先生と呼ばれ一目置かれます。
公認会計士として独立するということは、監査法人に勤務しているという肩書きを捨てることになります。
独立失敗のリスク
公認会計士として独立後、成功して高収入を得るようになることが望ましいですが、必ずしも成功するとは限りません。
その場合でも、公認会計士としての資格があれば、方向転換は可能です。
監査業務という独占業務があるため、監査法人に戻ることが最も確実な選択肢です。
監査法人は人手不足の傾向がありますし、働き方改革でひとりあたりの残業を減らそうとしていますので、監査の経験があれば歓迎されるでしょう。
独立後の年収についてはこちらもご覧ください。
独立失敗を避けるには?よくある失敗例とその対策
公認会計士は会計の高度な専門知識を有するプロフェッショナルであり、高い需要を誇ります。
しかし、需要が高いとはいえ必ずしも仕事を得られるとは限りません。
それどころか、独立開業で失敗した事例が多く存在するのも事実です。
この章では公認会計士の独立開業でよくある失敗例と対策について解説します。
営業活動の行き詰まり
失敗例としてよくみられるのが営業活動の行き詰まりです。
公認会計士に需要があるとはいえ、個人で事務所を運営する公認会計士は多数存在します。
そのため仕事を受けるためには営業活動が必須です。何もせず仕事が舞い込んでくるわけではありません。
営業やマーケティングに疎い人や苦手な人は営業活動が上手くいかず、案件を獲得できない事態に陥りがちです。
営業活動を軽視しており事前の準備や勉強が不足していた場合に起こりやすい失敗といえます。
価格競争で優位に立てない
価格設定に失敗し、価格競争で負けてしまい案件を獲得できないという失敗事例も多いです。
価格が高すぎると、同じようなサービスをより安価に提供するライバル会計士が選ばれてしまいます。
反対に価格が安すぎると、労力のわりに利益が少なく、働いても働いても稼げないという事態に陥りやすいです。
また「価格設定が安価な会計士事務所」のイメージが定着してしまうと、後の値上げが難しいというデメリットもあります。
競争優位性を意識しつつも、相場を外れすぎない適切な料金設定にしましょう。
差別化・ブランディングの失敗
差別化やブランディングに失敗し、クライアントに選んでもらえないという失敗事例もみられます。
先述のように、個人で事務所を運営する公認会計士は数多く存在します。
数ある選択肢の中から自身を選んでもらうには、「選ばれる理由」が必要です。
差別化やブランディングをしなければクライアントにとって選ぶ理由が見つからず、依頼につながりません。
また、ブランディングの内容と実際の特徴や強みが一致していなければ、顧客満足度や継続に至らないでしょう。
差別化やブランディングのためには、まずは自身の得意分野やアピールポイントの明確化が必要です。
その上で、クライアントに差別化ポイントを知ってもらうため、事務所の公式サイトやセミナー等で強くアピールする必要があります。
ライバルである他の公認会計士に負けないためには、差別化やブランディングに力を入れることが大切です。
公認会計士として独立に向くタイプは?
仕事への積極的姿勢がある
監査法人では、マネージャーまでは与えられた業務を的確にこなすことが求められます。
もちろんリーダーシップや創造性などを発揮する場面もありますが、基本的には監査人としての姿勢が求められます。
一方、独立後に必要なのは自分で仕事を獲得していく営業力や積極性です。
初めての業務、初めての業界、初めて会うタイプの経営者もいるでしょう。
切り開いていく積極的姿勢が必要です。
学び続ける姿勢がある
公認会計士として独立後は、監査法人にいた時のように、大きな案件に関わる機会は圧倒的に減ることが考えられます。
しかし、会計の専門家としてクライアントの期待に添い続けるには、常に新しい知識を吸収していく必要があります。
それには、謙虚に学び続ける姿勢が大切です。
常に情報収集し、最先端の情報を理解し、アドバイスする域にまで到達しなければなりません。
メンタルが強い
公認会計士として独立した時に一番必要なのは、強いメンタルではないでしょうか。
独立当初は、なかなか事務所が軌道に乗らず、思うように収入が伸びない時代もあるでしょう。
不安になって、弱気になることもあるかもしれません。
それでも自分が決断した「公認会計士としての独立」という目標の成功を信じて、地道に努力を続けるには、強いメンタルの維持が大切と言えるでしょう。
公認会計士が独立に踏み切るタイミングは?
高収入と言われる公認会計士は、監査法人に勤務しているならば平均年収は約800万円と言われます。
それほどの高収入を捨ててまで独立に踏み切るタイミングはどんな時なのでしょうか。
今いる場所で十分な経験を積んだと感じたとき
監査の仕事は、独占業務であり、非常に重要なものですが、長く続けると「もう十分だ」と感じることが多いようです。
また、チャンスをもらい、IPO支援やM&A、コンサルティング業務など経験するうちに、知識を蓄積、これを自分の専門分野にしたうえで独立したいと感じる人もいます。
今いる場所から飛び出すのは、勇気がいるものです。
変化を求め、独立する公認会計士は多数います。
独立したいと思ったとき
もっとシンプルに、独立したいと思ったときに一歩踏み出すという公認会計士も多いようです。
入念な準備をしたとしても、独立には常に「仕事がなくなるかもしれない」「自分自身で責任を取らなければならない」といったリスクがつきまといます。
家族がいる公認会計士ならば、より一層勇気がいる決断となるでしょう。
それでも独立をしたい、と思ったときがふさわしいタイミングだという意見もあります。
逆に言えば、迷いがあるならばまだ独立すべきではないというのが主流の考えです。
まとめ
公認会計士の独立後の仕事内容、独立をするために必要な準備、独立するメリット・デメリット、独立に向くタイプについて説明しました。
独立開業した公認会計士の平均年収は、公認会計士全体の平均年収を上回るといわれています。
上手くいけば1,000万円を大きく上回る高年収も実現可能です。
しかし、独立開業した公認会計士の年収は、報酬単価や仕事量によって大きく左右されるため一概にはいえません。
案件の内容や量によっては、公認会計士全体の平均年収を大きく下回る年収になる恐れもあります。
そのため、「独立すれば高年収を得られる」という思い込みは危険です。
また、公認会計士の独立にはメリットだけでなくデメリットも存在します。
公認会計士は需要が高い仕事とはいえ、独立すれば必ず成功するとは限らず、失敗事例が多く存在するのも事実です。
無理に独立をするのではなく、転職やフリーランスへの転身など別の方法をとる方が良いケースもあります。
独立の方法にも、積極的に事業展開する方法もあれば、地道な経営を選ぶ方法もあるでしょう。
共通するのは、公認会計士として独立する道を選ぶのであれば、常に新しい知識を追い求め、学び続ける積極的な姿勢が重要なことです。
ご自身にあった道を選択していってください。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
企業別インタビュー
転職成功ノウハウ
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ