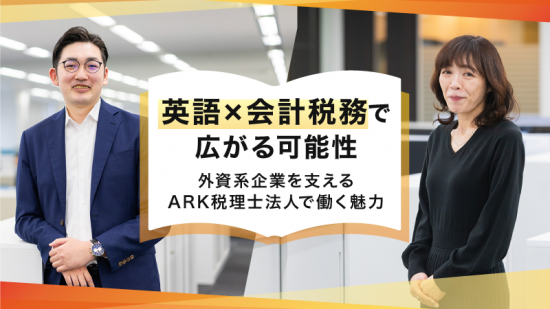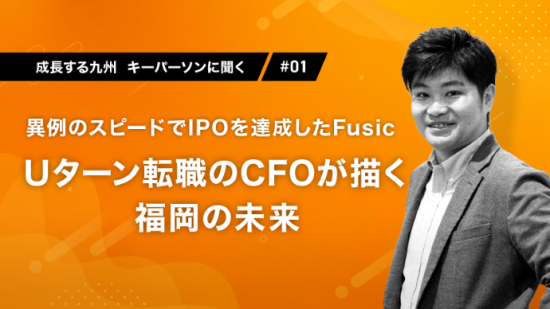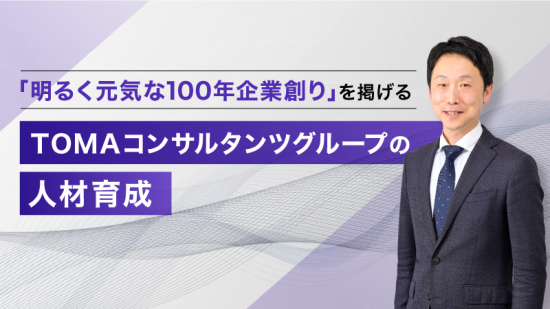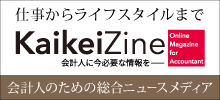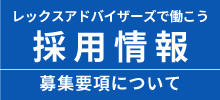転職お役立ち情報

税理士試験を受験するさい、学歴は必要なのかといった、気になることが多いでしょう。
税理士資格を得るには、税理士試験に合格しなければなりません。
試験の概要や難易度、取得すべき科目、合格までの勉強時間など、税理士受験生が気になるポイントを解説します。
税理士試験の概要
税理士試験を受験するにあたって、まずは試験制度を知ることが重要です。
税理士試験に学歴は必要かなど、試験制度の概要を解説します。
税理士試験の資格取得までの道のり
税理士試験では5科目合格する必要があります。
それぞれ必須科目、選択必須科目、選択科目に分けられます。
必須科目は2科目、選択必須科目は少なくとも1科目の合格が必要です。
受験生は自分で科目を選択して受験することになります。
また、試験は全科目を1年で合格する必要はありません。
科目合格制なので、自分で受験するペースを選ぶことが可能です。
試験は3日間に分かれて行われます。
自分が受験する科目の時に行くという形です。
それぞれの科目の合格点は60%で設定されており、合格率は10%〜15%程度で10%後半の合格率のものもあります。
なお、税理士試験は受験資格もあり、それを満たさなければ受験することができません。
しかし、令和5年からの試験では受験資格が緩和されます。
後述する必須科目である会計学科目は受験資格が撤廃されました。
また、税法科目の受験資格も緩和されたので、全体として受験しやすくなりました。
税理士試験の受験科目
税理士の受験科目をみていきましょう。
必須科目
- 簿記論
- 財務諸表論
選択必須科目
- 法人税法
- 所得税法
選択科目
- 消費税法
- 酒税法
- 事業税
- 住民税
- 相続税法
- 固定資産税
- 国税徴収法
全11科目です。
全ての科目が試験範囲の広さや特徴が同じではありません。
選択科目をいかにうまく選ぶかが短期間に合格まで結びつけられるポイントとなります。
税理士試験受験科目の取得方法
必須科目と選択必須科目は選択する余地がありませんが、選択科目についてはそれぞれ勉強時間が異なります。
そのため、選択科目をどの科目選ぶかが受験戦略上重要なポイントです。
勉強時間、計算あるいは理論の配分、実務上の要否などを加味して選択します。
実務上必要となる場合、選択必須科目を2つとも選ぶことも可能です。
ただし、それぞれの科目は受験科目の中でも1、2を争う試験範囲の広さで習得するにも時間がかかってしまいます。
受験と割り切り、その他の科目を受験。
合格してから実務で身につけるということも選択肢になります。
会計事務所への転職を希望されている方向け
転職相談会
税理士受験生の勉強時間はどれくらい必要か
次にここまで見てきた試験科目ですが、それぞれ勉強にかかる時間は異なります。
また、全体で5科目の合格が必要となりますが全体でどれぐらい時間がかかるのかについて解説していきます。
科目ごとに勉強時間が異なる
税理士試験は全11科目ありますが、それぞれ勉強時間は異なります。
以下の表はあくまで平均的な勉強時間であるため、人によっては簿記1級などの勉強をしていれば簿記論の勉強時間は短くなるでしょうし、また実務をやっていれば短くなります。
それぞれ状況が異なるので参考にしてもらえたら良いかと思います。
| 科目 | 平均的な勉強時間 |
| 簿記論 | 450時間 |
| 財務諸表論 | 450時間 |
| 法人税法 | 600時間 |
| 所得税法 | 600時間 |
| 消費税法 | 300時間 |
| 酒税法 | 150時間 |
| 事業税 | 200時間 |
| 住民税 | 200時間 |
| 相続税法 | 450時間 |
| 固定資産税 | 250時間 |
| 国税徴収法 | 150時間 |
必須科目や選択必須科目はそこまで勉強時間は変わりません。
選択科目は科目によってばらつきがあります。
これらを参考に選択科目を選んでいくのが良いでしょう。
5科目の勉強時間は
では、5科目を合格することになる税理士試験はどれぐらいの時間勉強することになるのでしょうか。
先ほどの表はあくまで目安ですが、5科目でだいたい2,000時間以上3,000時間程度はかかると言われています。
もちろんどの科目を選択するかによって変わりますが、だいたい全科目を合格するにも3年〜5年程度かかります。
科目合格制なのでうまく科目を選択して受験をしましょう。
科目ごとに異なるので効率的に進めよう
平均的な勉強時間は上記ですが、科目によって計算の方に重きを置かれていたり、理論の方に重きを置かれていたりとそれぞれ違いがあります。
わかりやすい例でいけば、国税徴収法は理論が100%となっています。
理論が得意な人にとったら選ぶべき科目で理論が苦手な人にとっては選ぶべき科目ではありません。
また、科目合格制の税理士試験は、1年で勉強する科目も選び方も重要です。
順番を考えながら受験することで効率的に取得することができます。
税理士受験生に学歴は必要か
税理士試験を受験するにあたって、学歴は影響するのでしょうか。
税理士受験生の学歴について解説していきます。
税理士受験に学歴は必要?
税理士受験に学歴が必要かと言われると、結論、必要ありません。
むしろ高学歴の税理士は少ないと言えます。
実は、早慶上智出身はあまりいません。
関関同立やMARCHの方が多いイメージです。
一般的に思われるような超高学歴な人が多いわけではないというのが、税理士の実態となります。
税理士の就職には学歴が影響するか
では税理士の就職に学歴が必要になるかというと、そこも必要にはなりません。
一般的な就職であれば学歴が良い方がいいでしょう。
税理士は学歴よりも受験科目やそれまでの経験が重視されます。
学歴は関係ありません。
むしろ今後のキャリアを合わせて受験科目や経験などを考えてキャリアを積むことが重要になります。
学歴が高いと開業しやすい?
税理士において開業する人も多いですが、ここにおいても学歴は影響ありません。
ここでも就職等と同様、受験科目、経験などが重要です。
就職と異なるのは、コミュニケーション能力という点でしょう。
開業すると仕事は顧客からもらうことになり、顧客との関係性というのが重要になります。
学歴が高ければ仕事をもらえるという世界ではありません。
いかに経験を積んで顧客との関係性を構築するかがポイントです。
税理士受験生の年齢は高い?低い?
税理士の受験生はどのような年齢層が多いのでしょうか。
今からでも挑戦できるのか、不安という人もいるかもしれません。
税理士受験生の年齢について解説します。
税理士合格者の年齢は40代以上も意外に多い
税理士試験の合格者では、一部科目合格者も全科目合格者も41歳以上が一番多い人数となっています。
資格試験は若い年齢層が多いイメージかもしれません。
税理士試験に限って言えば年齢層が高くても低くても関係なく合格ができる試験となっています。
これまでは税理士試験の受験資格が厳しいものでした。
大学の専攻科目が限られていたり簿記1級などの要件が厳しかったりしたことが影響して、若い世代が少なかったと考えられます。
上述した通り、受験要件が緩和されたので今後どのような流れになるか注目です。
平均年齢が高い理由は?
平均年齢が高いのは上述した受験要件もそうですが、そのほかにも要因があると考えられます。
税理士は資格さえ取れば長く働くことができます。
若い時に取らなくても良い資格と考えられているのかもしれません。
また、科目合格制が採用されているので、全科目を合格するのには時間を要しても問題ないことも理由でしょう。
国税従事者は試験を免除されるので、受験するタイミングが遅くなることも多いです。
こうした要因で平均年齢が高めになっています。
受験を目指せる限界は?
では受験を目指す限界はあるのでしょうか。
結論、限界はありません。過去には70歳代で合格した人もいます。
限界はないと考えて良いでしょう。
ただし、取得した後のキャリアがあるため、いくら長く働けるとはいえ、若い方が望ましいのは事実です。
できるだけ早く取得する方が有利であることに違いはありません。
まとめ
ここまで学歴など、税理士受験生が気になるポイントについて解説してきました。
税理士試験受験において、選択する科目はとても重要です。
効率的に習得し合格しましょう。
勉強していない科目に関しても、必要に応じて実務で学べば問題ありません。
業務も行うことができるでしょう。
経験を積むとともに、顧客との関係を構築することも大切になります。
税理士として充実した生活を送るための第一歩となる受験勉強。
この記事が助けになれば幸いです。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
企業別インタビュー
転職成功ノウハウ
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ