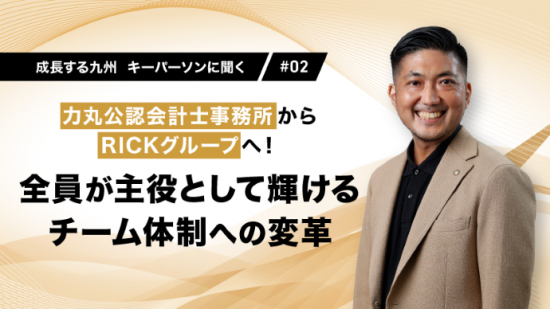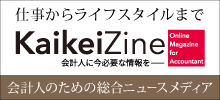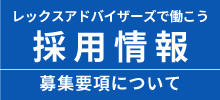転職お役立ち情報

日本における三大国家資格とは、弁護士・公認会計士・不動産鑑定士の3つの専門職を指します。
どの資格も高い社会的地位と高収入が期待できますが、非常に難易度が高く、取得までの道は険しいものです。
今回は三大国家資格である弁護士・公認会計士・不動産鑑定士について詳しく解説します。
【この記事からわかること】
- 弁護士・公認会計士・不動産鑑定士それぞれの取得のために必要な試験や合格率
- 弁護士・公認会計士・不動産鑑定士それぞれの年収
- 三大国家資格以外の難関資格の例
三大国家資格とは何か?

三大国家資格とは、日本の国家資格の中でも特に難易度が高い資格を指す言葉です。
日本における三大国家資格として、弁護士・公認会計士・不動産鑑定士が挙げられます。
いずれも取得が難しい上に重要性や専門性も高く、取得することで高い社会的地位と高収入が期待できます。
なお、三大国家資格に不動産鑑定士ではなく医師を入れるケースも多いです。
医師免許も取得が難しく必要性や専門性が高い点も他2つの資格と共通していますが、医師国家試験自体よりも大学入試の方が重要です。
したがって、資格試験自体の難易度や年収を比較するという趣旨からはやや逸れてしまう恐れがあります。
以上の理由から、本記事では弁護士・公認会計士・不動産鑑定士の3つを三大国家資格として扱います。
三大国家資格1:弁護士について
弁護士とは法律に基づいて依頼者の権利を守り、法的な助言や事件・紛争などの代理を行う専門職です。
この章では弁護士資格について詳しく解説します。
弁護士資格のために必要な試験
弁護士資格を取得するためには司法試験に合格する必要があります。
厳密に言うと、司法試験は弁護士だけでなく、裁判官や検察官を含む法曹資格を取得するために合格が必要な試験です。
司法試験を受けるには以下いずれかの受験資格を満たす必要があります。
- 法科大学院を修了している
- 司法試験予備試験に合格している
司法試験予備試験および司法試験はいずれも年に1回のみ実施されます。
令和7年度の実施日程は以下の通りでした。
出典:令和7年司法試験予備試験の実施日程等について、令和7年司法試験の実施日程等について
|
司法試験予備試験 |
【短答式試験】 令和7年7月20日
【論文式試験】 令和7年9月6日、7日
【口述試験】 令和8年1月24日、25日 |
|
司法試験 |
【論文式試験】 7月16日、17日、19日
【短答式試験】 7月20日 |
弁護士試験の合格率
前述のように、司法試験を受けるには法科大学院の修了または予備試験に合格する必要があります。
この章では予備試験と司法試験それぞれの合格率を紹介します。
【令和6年司法試験予備試験 合格率】
|
短答式試験 |
約22% |
|
論文式試験 |
約18% |
|
口述試験 |
約97% |
|
最終的な合格率 (短答式試験の採点対象者のうち口述試験の合格者が占める割合) |
約3.6% |
【令和6年司法試験 合格率】
|
短答式試験 |
約80% |
|
論文式試験 |
約42% |
出典:令和6年司法試験(短答式試験)の結果、令和6年司法試験の採点結果
司法試験自体の最終的な合格率は40%ほどで、これだけをみると合格率が高いように感じるかもしれません。
しかし予備試験の最終的な合格率は4%以下と非常に低い数値です。
したがって、弁護士試験の難易度は非常に高いといえるでしょう。
弁護士の年収の目安
日本弁護士連合会が発行する弁護士白書の中で、弁護士の平均年収や所得が紹介されています。
それぞれの金額は以下の通りです。
|
平均年収 |
2,082.6万円 |
|
所得の中央値 |
800万円 |
|
所得の中央値 |
1,022.3万円 |
また、回答者のうち10%は年収5,000万円以上です。
弁護士は取得難易度が非常に高いですが、その分かなりの高年収を得られる資格・職業といえるでしょう。
忙しいあなたのための電話転職相談
三大国家資格2: 公認会計士について
公認会計士は会計分野における最高峰の資格で、企業の財務情報の信頼性を保証するプロフェッショナルです。
独占業務である監査をはじめ、会計関連の高度なサービスを提供します。
公認会計士資格のために必要な試験
公認会計士資格を取得するためには、以下3つの条件をクリアする必要があります。
- 公認会計士試験に合格する
- 3年以上の実務経験および実務補修を受講する
- 修了考査に合格する
中でも最もハードルが高いのが1の公認会計士試験です。
公認会計士試験は1次試験である短答式試験と、2次試験である論文式試験の2つに合格する必要があります。
試験に合格するだけでなく、3年間の実務経験の要件および実務補修の受講という要件も満たす必要があります。
試験に合格してから実務経験を行い、並行して実務補修を受講するのが一般的です。
実務補修で必要な単位をすべて取得した後は修了考査を受けられるようになります。
修了考査に合格することで公認会計士登録が可能になります。
公認会計士試験の合格率
前述のように、公認会計士試験は短答式試験と論文式試験という2つの試験から構成されています。
それぞれの直近5回分の合格率は以下の通りです。
【短答式試験】
|
開催年度・回 |
合格率 |
|
令和7年第Ⅱ回 |
9.2% |
|
令和7年第Ⅰ回 |
11.2% |
|
令和6年第Ⅱ回 |
9.5% |
|
令和6年第Ⅰ回 |
10.8% |
|
令和5年第Ⅱ回 |
8.8% |
【論文式試験】
|
開催年度 |
合格率 |
|
令和6年 |
36.8% |
|
令和5年 |
36.8% |
|
令和4年 |
35.8% |
|
令和3年 |
34.1% |
|
令和2年 |
35.9% |
短答式試験の合格率は10%前後、論文式試験は35%前後と、どちらも非常に難易度が高いことが伺えます。
公認会計士試験は試験分野がとても幅広いため、膨大な量の勉強が必要です。
公認会計士の年収の目安
公認会計士の年収目安は年齢や経験年数、勤務先によって大きく異なります。
参考として、年代別の平均年収を紹介します。
- 20代:600万円前後
- 30代前半:800万円台
- 30代後半:1,000万円前後
- 40代以降:1,000万円以上
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、令和5年度の給与所得者の平均給与は460万円でした。
前述のように、20代の公認会計士の年収目安は600万円前後です。
すなわち公認会計士は20代の時点で、日本の平均を大きく上回る年収を得られる可能性があるといえるでしょう。
なお、監査法人のマネージャーやパートナーに就任する、独立開業し成功する等の方法により年収2,000万円を実現する公認会計士もみられます。
公認会計士の求人情報はこちら
三大国家資格3:不動産鑑定士について
不動産鑑定士とは土地や建物など不動産の価値を鑑定するプロフェッショナルです。
不動産鑑定評価基準に基づき、不動産の適正な経済的価値を公正かつ客観的に評価します。
不動産鑑定士資格のために必要な試験
不動産鑑定士の資格を取得するには、以下3つの条件を満たす必要があります。
- 国土交通省による不動産鑑定士試験に合格する
- 実務修習機関で実務修習を受講する
- 実務修習の各課程修了後に受験できる「修了考査」に合格する
2の実務補修は1年コースと2年コースのいずれか好きな方を選択可能です。
講義、基本演習、実地演習の3単元から構成されており、すべての単元で修得確認を得る必要があります。
なお2025年7月時点で実務修習機関として登録を受けているのは日本不動産鑑定士協会連合会のみです。
不動産鑑定士試験の合格率
不動産鑑定士試験は一次試験である短答式試験と、二次試験である論文式試験から構成されています。
それぞれの直近5年分の合格率は以下の通りです。
【短答式試験】
|
開催年度 |
合格率 |
|
令和7年 |
約36.3% |
|
令和6年 |
約36.1% |
|
令和5年 |
約33.6% |
|
令和4年 |
約36.3% |
|
令和3年 |
約36.3% |
【論文式試験】
|
開催年度 |
合格率 |
|
令和6年 |
約17.4% |
|
令和5年 |
約16.5% |
|
令和4年 |
約16.4% |
|
令和3年 |
約16.7% |
|
令和2年 |
約17.7% |
出典:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験結果情報 - 国土交通省
短答式試験は35%前後、論文式試験は16~18%と合格率が低く、難易度が高いと判断できます。
不動産鑑定士の年収の目安
厚生労働省の運営する職業情報提供サイトによると、不動産鑑定士の平均年収は591万円です。
時間当たりの賃金や月額の求人賃金は以下の通りです。
|
1時間あたり賃金(一般労働者) |
2,967円 |
|
1時間あたり賃金(短時間労働者) |
2,048円 |
|
求人賃金(月額) |
26.9万円 |
出典:不動産鑑定士 - 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)
不動産鑑定士の主な勤務先として、不動産鑑定事務所、不動産会社、金融機関、建設・土木会社などが挙げられます。
不動産コンサルタントとして活動する不動産鑑定士もみられます。
三大国家資格以外の難関資格について
これまでに紹介した三大国家資格以外にも、難関資格と呼ばれる国家資格は複数存在します。
今回は三大国家資格以外の難関資格のうち、特に有名といえる以下3つの資格を取り上げました。
- 税理士
- 司法書士
- 弁理士
それぞれの仕事内容や試験合格までにかかる時間の目安などを紹介します。
税理士について
税理士は税理士法に基づく国家資格です。
税務のプロフェッショナルとして、企業や個人の税務相談や税務代行などを行います。
前述した公認会計士との大きな違いは独占業務です。それぞれ以下のような独占業務をもちます。
|
公認会計士 |
税理士 |
|
財務諸表の監査および内容証明 |
|
また、公認会計士の主なクライアントは監査が必要である上場企業や大企業ですが、税理士の主なクライアントは中小企業や個人となります。
税理士資格を取得するには、税理士試験の合格および2年以上の実務経験が必要です。
税理士試験は全11科目から構成されており、必須2科目、選択必須1科目、選択2科目の計5科目に合格する必要があります。
5科目合格までに必要な勉強時間の目安は最低2,000時間、平均4,000時間といわれています。
税理士の求人情報
司法書士について
司法書士とは登記や供託等の法律事務を専門とする国家資格です。
今回紹介した弁護士は、法律トラブルに関する相談や訴訟・裁判の代理等が主な業務です。
一方で司法書士は事件が起きてからの対応ではなく、訴訟や紛争を予防するための法律事務手続きを専門としています。
また近年は高齢化の影響により、成年後見人(認知症などで正常な財産管理が難しくなった成人の財産管理支援者)を務めるケースも増加傾向です。
司法書士になるには法務省が実施する司法書士試験に合格する必要があります。
勉強時間の目安は3,000時間程度です。
弁理士について
弁理士は知的財産に関する専門家で、主に特許等の申請手続きの代行や関連する書類の作成などを行います。
また、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した弁理士であれば、特定侵害訴訟における訴訟代理人になることもできます。
近年はグローバル展開をする企業が増えているため、海外での特許申請に関する需要も高いです。
弁理士になるには弁理士試験の合格が必要する必要があります。
必要な勉強時間の目安は3,000時間程度といわれています。
まとめ
日本の三大国家資格である弁護士・公認会計士・不動産鑑定士は、いずれも取得難易度が非常に高いです。
合格率が10%を切る試験も多く、取得までの道は非常に険しいといえます。
しかし資格を取得できれば、高い社会的地位や高年収を実現できるでしょう。
一口に三大国家資格といっても、資格によって試験の形式やポイントは全く異なります。
複数の資格を比較して大まかな特徴を掴んだ後、気になる資格があればさらに詳しく調べてみるのが良いでしょう。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
企業別インタビュー
転職成功ノウハウ
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ