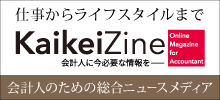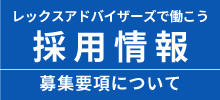転職お役立ち情報

税理士業務の基本は、記帳代行や税務申告書の作成などです。
しかし、今後AIやRPAが普及すると、そういった定型的業務しか行っていない税理士は生き残っていけないのではないかと一部では懸念されています。
そんな状況の中で税理士として生き残り、成長していくための戦略として、より専門的な業務に携わっていくことが重要です。
税務デューデリジェンスもそんな専門的な業務の一つであり、現在、ニーズが非常に高まっている分野です。
この記事では税務デューデリジェンスの概要と、税務デューデリジェンスにはどのような人が向いているかについて解説していきます。
1.デューデリジェンスとは?
デューデリジェンス(Due Diligence、DD)とは、投資を行うにあたり企業など投資先の価値やリスクなどについて行う調査のことです。
デューデリジェンスには、
- 組織や財務活動について調査する『ビジネス・デューデリジェンス』
- 財務内容などからリスクを調べる『財務デューデリジェンス』
- 定款や登記事項など法的側面をチェックする『法務デューデリジェンス』
- 税務のリスクを把握する『税務デューデリジェンス』
などの種類があります。
デューデリジェンスを行う前段階として、投資元と投資先とが秘密保持契約を締結。
その上で投資先から投資元に情報が開示され、投資元はその情報から企業価値や事業リスクを判断し、一応の買収価格を決定することになります。
ただし、投資先から提供された情報だけをそのまま鵜呑みにするのではなく、提供された情報に間違いはないか、今後何らかの問題が生じる恐れはないかなど、投資先の実態を投資元の観点から調査する必要があります。
そういった調査などがデューデリジェンスと呼ばれます。
2.デューデリジェンスを実施する目的
デューデリジェンスを実施する目的はいくつかあり、以下のようなものがあります。
a.投資先が自社のM&A戦略に照らし合わせて適合しているかの確認
買収元のM&A戦略に適合していない買収先を買収してしまうと、買収元にとって大きな危機となるリスクが高いです。
そのため、買収先が買収元のM&A戦略に照らし合わせて適合しているかの確認が綿密に行われます。
b.デューデリジェンスでの発見事項を織り込んだ買収価格の算定
例えば、買収先が株式を上場している企業であったとしても、単に現在の株価を見るだけでは適正な買収価格を算定できません。
買収元が現在既に行っている事業とのシナジーや買収先の財政状態などを総合的に勘案する必要があります。
当然、考慮しなければならない要素の中にデューデリジェンスを通じて発見した事項も含まれます。
c.当初意図していたM&Aのスキームでよいかの確認
一口にM&Aと言っても様々なスキームが考えられる上、どういったM&Aのスキームを用いるかで税金の額も大きく変わります。
そのため、デューデリジェンスを通じて、当初意図していたM&Aのスキームが本当に最適であるかを確認します。
d.買収後に発生する可能性の高い問題を事前に把握しその対応策を用意
買収自体さえ上手くいけばそれでよいということではなく、実際に買収した後も事業が継続し発展するようにM&Aを行う必要があります。
そのため、買収した後に起こりうる様々な問題について把握し、対応策を考えておく必要があります。
希望の条件を妥協しない!今の働き方を変えたい
税理士・税理士科目合格者向け
転職相談会
3.税務デューデリジェンスとは?
何種類かあるデューデリジェンスの内、税務デューデリジェンスでは、買収及び買収後に重要な影響を与える税務リスクを洗い出し、対策を講じます。
具体的には、以下のような手続を行います。
a.買収先の経営層および税務アドバイザーに対するインタビュー
経営層および税務アドバイザーに対して質問などを行い、買収先の税務の状況を把握し問題点を洗い出します。
b.税務申告書のチェック
買収先が税務署に提出した税務申告書をチェックし、今までの納税状態を把握します。
c.税務に係るコンプライアンスおよび内部統制についての理解
買収先の税務に関わるコンプライアンスや内部統制について確認します。
これは買収先が税務リスクをどのように把握し、どのような税務リスクに対応しているかを理解するためです。
d.税務調査・税務訴訟等、税務署への対応状況の把握
企業がいくら税金を払わなければならないかを決めるのは法律およびその解釈によって必要な対応をとる税務署です。
税務署への対応が上手くいっていないと大きな税務リスクになりうるため、税務署への対応状況についてはしっかりと把握します。
e.移転価格税制に対する対応方針・移転価格に関する文書化の状況の把握
国際税制の中でも移転価格税制は、特に専門的であり、企業への影響の大きい税制です。
そのため移転価格税制への対応方針や文書化の状況については特に注意して把握します。
f.過去の資本取引や組織再編に関する税務の把握
組織再編や株主構成の変化は事業全体に対して大きな影響を当たる事柄です。
当然、税務にも大きな影響を与えるため、その全体像を掴み、そこから発生しうる税務リスクについて把握します。
g.関連当事者との取引の内容の把握
関連当事者との取引は企業にとって様々なリスクとなりうる取引です。
もちろん、税務リスクも発生しやすいため、あらかじめ内容を把握しておく必要があります。
h.税務上の欠損金や優遇税制などの把握
税金を減額できる要因を把握し、買収後の節税に活かす必要があります。
4.税務デューデリジェンスに向いている人
ここまで税務デューデリジェンスの概要について見てきました。
ここでは、税務デューデリジェンスに向いている人についてご紹介します。
a.税務デューデリジェンスは定型的業務ではないため変化に強い人
記帳代行などと異なり、毎回行うべき業務がほぼ同じであるというような状況は、まず発生しません。
日々変化し続ける状況への対応が必要です。
そのため変化に強くその時その時で適切な対応を取れる人が、税務デューデリジェンスに向いています。
b.利害関係が複雑なので上手に人間関係に対応できる人
M&Aにあたっては、様々な方が多種多様な考えを持って行動することになります。
そのため、利害関係は非常に複雑です。
そういった中で、上手に人間関係に対応できる方が税務デューデリジェンスに向いていると言えます。
c.組織再編は多くの方に影響を与える事柄なのでタフな人
M&Aはオーナーや経営陣だけではなく、多数の従業員にも非常に大きな影響を与えます。
M&A後に大規模な人員削減が行われるという流れになることもありえます。
そのため、M&A関連の業務に携わるにはタフである必要があるのです。
d.専門的な知識があるだけではなく、それらを使ってしっかりとコミュニケーションが取れる人
クライアントは税理士がある程度の専門知識を持っていることは当然であると考えています。
ただ知識を持っているというだけではなく、クライアントの役に立つ知識を、クライアントに分かりやすく説明して欲しいと願っています。
そのような要望に応えられるコミュニケーション能力をお持ちの方が税務デューデリジェンスに向いています。
5.まとめ
ここまで、税務デューデリジェンスの概要と税務デューデリジェンスはどのような人が向いているかについて見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
税務デューデリジェンスは、非常に専門的であると同時に、過酷と言えなくもない面がある業務です。
ただし、業務の中に税理士として大きく成長できる機会がたくさん用意されています。
税務デューデリジェンスにチャレンジしたい人は転職を成功させ、キャリアをより輝かしいものにしていって下さい。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ