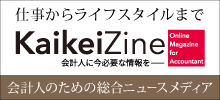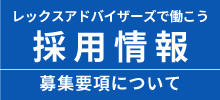転職お役立ち情報

社労士(社会保険労務士)資格をとるための難易度はどれくらいなのでしょうか。
社労士は国家資格の1つです。
受験をし、合格するまでに相当量の勉強が必要というイメージがあります。
しっかりとした対策がなければ合格はできません。
合格率や必要な勉強量などを解説していきましょう。
社労士試験だけでは難易度の測定が難しいので、他の国家資格とも比較します。
社労士資格試験の概要
はじめに、社労士資格試験の概要を紹介します。
|
試験日程 |
● 試験詳細の公開:4月 ● 受験申込期間:4月中旬~5月31日 ● 試験日:8月の第4日曜日 ● 合格発表:10月上旬 |
|
当日のスケジュール |
午前:選択式試験(80分) 午後:択一式試験(210分) |
|
試験科目数 |
選択式試験:計8科目 択一式試験:計7科目 |
|
合格基準 |
選択式および択一式それぞれの総得点および科目ごとに定める ※いずれか1つでも合格基準に達しない場合は不合格 |
|
受験手数料 |
15,000円 |
試験は毎年8月の第4日曜日に1日がかりで行われます。
試験時間が長く科目数も多いため、体調管理やペース配分も非常に重要といえるでしょう。
また各試験形式および科目のうち1つでも合格基準に届かなかった場合、総得点に関係なく不合格になる点にも注意が必要です。
試験日程
社労士試験の大まかなスケジュールは以下の通りです。
- 試験詳細の公開:4月
- 受験申込期間:4月中旬~5月31日
- 試験日:8月の第4日曜日 ※令和6年度試験は8月25日(日)
- 合格発表:10月上旬 ※令和6年度試験は10月2日(水)
試験は1日かけて行われます。
午前中に選択式試験、昼食時間を挟んで午後に択一式試験が行われます。
令和6年度試験の当日の流れは以下の通りでした。
|
午前 (選択式試験) |
開場時間 |
9時30分 |
|
着席時間 |
10時 |
|
|
試験開始 |
10時30分 |
|
|
試験終了 |
11時50分 |
|
|
昼食時間 |
11時50分~12時50分 |
|
|
午後 (択一式試験) |
着席時間 |
12時50分 |
|
試験開始 |
13時20分 |
|
|
試験終了 |
16時50分 |
|
どちらも試験開始直後および試験終了直前に退室禁止時間が定められています。
試験の出題形式
試験の出題形式は選択式と択一式の2種類です。
前述のように午前中に選択式試験、午後に択一式試験が行われます。
選択式は文章中の空欄を埋めるのに適切な語句を選ぶ形式です。
単純な知識だけではなく、問われていることを正しく理解するための読解力も求められます。
択一式は複数の選択肢から問題に対する回答に適したものを1つ選ぶ形式です。
正解の選択肢1つを選ぶ問題もあれば「正しいものはいくつあるか」「正しい組み合わせはどれか」といった問いもあります。
社労士試験の科目数
社労士試験の出題範囲は「労働法関係」と「社会保障関係」の2分野です。
各範囲の出題科目は4科目ずつ、合計8科目となります。
試験の出題形式で紹介したように、試験形式は選択式と択一式の2種類があります。
選択式の出題科目は8科目、択一式の出題科目は7科目です。
試験科目・試験形式・各科目の問題数・配点をまとめると以下のようになります。
|
試験科目 |
試験形式および配点 |
|
|
選択式 |
択一式 |
|
|
労働基準法・労働安全衛生法 |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
労務管理その他の労働に関する一般常識 |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
社会保険に関する一般常識 |
1問(5点) |
|
|
健康保険法 |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
厚生年金保険法 |
1問(5点) |
10問(10点) |
|
国民年金法 |
1問(5点) |
10問(10点) |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「社会保険労務士試験の概要」
※選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に関する出題はありません。
択一式の方は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」が1つの科目として扱われています。
なお合格基準点は、選択式・択一式それぞれの総得点と、各科目ごとに定められます。
1つでも合格基準点に満たないものがある場合、総得点に関係なく不合格となる仕組みです。
科目別の内容
社労士試験で出題される科目別の詳しい内容とポイントを紹介します。
※試験科目としては「労働基準法・労働安全衛生法」は同科目、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」は他の科目と一緒に出題されるものですが、ここでは独立した科目としてポイントを解説します。
|
労働基準法 |
内容 |
労働条件の最低基準を定めた法律。社労士の実務でも関わる場面が多い。 |
|
ポイント |
労働契約や労働条件といった基本事項を念頭に置きながら勉強を進める。判例等の長文問題も出やすい傾向のため、単純な暗記ではなく理解が必須。 |
|
|
労働安全衛生法 |
内容 |
労働災害からの保護や快適な労働環境の形成のための法律。主に安全衛生管理や健康管理について規定している。 |
|
ポイント |
労働安全衛生法ならではの用語も多いため、用語に慣れることが大切。安全衛生管理体制が頻出分野。 |
|
|
労働者災害補償保険法 |
内容 |
業務中や通勤中の怪我・病気などの補償制度を定めた法律。 |
|
ポイント |
保険給付の仕組みや支給要件が特に重要。給付通則についても多く出題される。 |
|
|
雇用保険法 |
内容 |
生活や雇用の安定を図る目的の法律。失業予防や労働者福祉の増進に関する規定も存在する。 |
|
ポイント |
労働基準法と並んで重要性が高い。被保険者、雇用保険事務、保険給付や就職促進給付の計算方法などが頻出分野・ |
|
|
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
内容 |
労災保険および雇用保険の保険料徴収方法や加入手続きなど、労働保険の事務手続きについて定めた法律。 |
|
ポイント |
前提知識として労働者災害補償保険法と雇用保険法の学習が必要。計算問題も多く出題される。 |
|
|
労務管理その他の労働に関する一般常識 |
内容 |
その他の労働関連法や労働経済・労務管理が広く出題される。 |
|
ポイント |
法律に関する知識だけではなく、労働統計や雇用動向のような情勢問題に関する情報収集も必須。 |
|
|
健康保険法 |
内容 |
業務外の怪我や疾病、出産、死亡等に対する保険給付を目的とした法律。 |
|
ポイント |
労働保険法と混同しないよう注意が必要。 |
|
|
厚生年金保険法 |
内容 |
会社員や公務員などが加入する厚生年金について規定した法律。 |
|
ポイント |
年金の仕組みを十分に理解する必要がある。前提知識として、健康保険法および国民年金法についての理解も必須。 |
|
|
国民年金法 |
内容 |
主に自営業者が加入する国民年金について規定した法律。 |
|
ポイント |
保険給付、被保険者、費用に関する出題が多い。基礎年金、共済年金、障害基礎年金など、年金の種類ごとの特徴を押さえることも大切。 |
|
|
社会保険に関する一般常識 |
内容 |
その他の社会保険関連法規や社会保険の歴史的沿革、最新動向など幅広く出題される。 |
|
ポイント |
問われる内容は基礎的なものが多いが出題範囲が広い。細かい論点まで学習するのでは際限ないため、学習範囲の下限が必要。 |
社労士試験合格に至るまでの道のり
社労士試験合格のための学習期間は、一般的には1年ほどです。
社労士試験の実施日程は毎年8月の第4日曜日なので、その前の年からスケジュールを組んで準備する人が多いようです。
例えば、2024年の社労士試験合格を目指す場合、2023年の8月から勉強を開始することになります。
そこまで勉強の期間が長いわけではありません。
また、社労士試験の平均合格回数は3-4回程度。
これは1-2回で合格する人と7-8回で合格する人の2極化の傾向があるからです。
短期で合格をするには、足切りにならないよう、全科目を総合的に勉強することが必要になります。
また、単に暗記するのではなく、出題内容を理解する勉強をおすすめします。
社労士試験は問題数が多いです。
択一式は210分の中で70問、選択式試験は、80分の中で40問 の出題がされるため、1問1問をスピーディに解いていかなければなりません。
問題を解く際は、そのスピードも意識して行いましょう。
過去問を解くことも重要です。
社労士資格の合格率
社労士試験の合格率は、2022年度は受験者数40,633人に対して合格者数2,134人でした。
合格率は5.3%です。
他の年度も総じて5%〜7%と、10%以下がほとんどなので、合格率は低いといえます。
社労士試験は大小含めて8科目と科目数が多く、幅広い知識を身につけなければなりません。
また足切りがあります。
足切りとは、選択式試験と択一式試験の2点がある社労士試験で、最低限とっておかなければならない点数基準です。
このラインは選択式各科目5点満点中3点、択一式各科目10点満点中4点が基本となっています。
科目毎に細かく足切りラインが決まっているのが社労士試験の特徴の1つといえます。
基礎を取りこぼさないことが重要です。
また、合格基準点は選択式、択一式共に総得点の65%以上程度となっています。
他の資格との難易度比較
社労士試験の合格率は5.3%ですが、他の試験の合格率も見てみましょう。
- 行政書士試験……10%前後
- 土地家屋調査士試験……8~10%
- 宅地建物取引士試験(宅建)……15%~20%前後
です。
比較すると、社労士試験の合格率はやや低めと言えます。
また、社労士試験と行政書士試験を比較してみましょう。
社労士試験は各科目に合格基準が設けられており、その基準を下回ってしまうと足切りとなり合格することができない仕組みになっています。
一方で、行政書士試験には科目毎の合格基準というのは設けられておりません。
そういった点では、社労士試験は試験難易度が高いと言えるでしょう。
なお、勉強時間の目安は社労士、行政書士共に約800時間~1,000時間となります。
必要といわれている勉強時間で比較すると、税理士約3,000時間、司法書士約3,000時間。
中小企業診断士約1,000時間です。
必要な勉強時間の差で考えるとこれらの資格試験よりは比較的取りやすい資格ともいえます。
経理・財務経験者向け
キャリアアップ転職相談
社労士資格を取得するにはどのくらい勉強すれば良い?
社労士試験は各科目に合格基準点という足切り要件があるため、各科目をまんべんなく勉強する必要があります。
1つの科目でも合格基準を満たしていないと不合格となるので、そういった意味で厳しい試験と言えます。
この合格基準点ですが、合格発表日に公表されるので、どこまでやっておけば安心という基準もまた設けにくいです。
そのため、社労士試験の勉強は他試験に比べやり方が違ってきます。
各科目と、必要な勉強時間について参考にし、勉強法を考えてみましょう。
社労士の資格取得には予備校に行くべきか?
ここまで社労士試験の内容と難易度について述べてきました。
社労士の資格取得には予備校にいくべきなのでしょうか。
一般的に予備校に行くにはそれなりのお金が必要となります。
また、社会人は仕事があり、勉強時間に制限があるので、悩ましいところです。
そこで、予備校に行くべき理由と独学の違いについて解説します。
予備校と独学での違い
まず、独学のメリットは自分で勉強時間を決められ、コストを安く抑えられるところです。
一方で、勉強をするための自己管理が難しかったり、そもそもどういった問題集を使えば合格レベルの実力が身に付くのかを考えたりしなければなりません。
自分でやることが多いことはデメリットでしょう。
社労士試験は科目毎に足切りが設定されているため、過去問を精査し、各科目に穴を空けない勉強法が必要です。
最近は無料で学べる機会も多くなっていますが、教材選びがかなり重要になります。
一方、予備校に通う場合、合格実績のあるカリキュラムやテキストなどを使って勉強することができます。
定期的にテストをするので、本番に備えて自身の実力を常に測りながら勉強できるのもメリットです。
周りはみな同じ受験生という環境もプラスに働くかもしれません。
また、法改正の最新情報をタイムリーに、必要なところだけおさえておいてくれます。
これも、法改正の影響を受けやすい社労士試験では大きなアドバンテージとして挙げられるでしょう。
予備校に行かないと資格取得は難しい?
さて、予備校に行かないと資格取得は難しいのでしょうか。
結論から言うと、独学で合格できるのは一部の人だけです。
予備校に行って受講するのが合格に手っ取り早い方法となります。
まず、独学は最短効率で勉強を進めるのが難しいものです。
いくら分野が限られているといっても広い範囲で勉強しなければ合格はできません。
基礎から解説してくれる予備校のテキストや教材であれば合格までの勉強が効率よくできるでしょう。
とりわけ、勉強時間の確保が難しい方は独学に向いていません。
できるだけ少ない勉強時間で合格できるよう、予備校の教材でピンポイントで学ぶ方法がおすすめです。
次に、周りに社労士試験について質問できる人がいない方も独学には向いていません。
講師に質問できるのも、予備校の強みでしょう。
試験勉強をしているとどうしてもわからない箇所がでてきます。
そこを自分で一から調べると余計な時間がかかってしまいます。
質問の答えをすぐ確認できると、勉強の効率がアップするでしょう。
社労士資格取得のための予備校選びでおさえておくべきポイント
社労士資格取得には予備校に通うのが効率が良いと先述しました。
予備校を選ぶうえで、通学と通信で比較した時におさえておくべきポイントは何でしょうか。
通学と通信との比較
まずは通学と通信を比較してみましょう。
基本的に直接講義を聞いた方が頭に入りやすいので、通学できればベストです。
講義で会った同じ受験生と勉強仲間になれればモチベーション維持にもなるでしょう。
もちろん、質問できる講師がすぐそばにいるので効率的に勉強できます。
しかし、予備校が家の近くにないなど、物理的に通学が難しい人もいるでしょう。
そうした場合は通信講座が便利です。
費用に関しましては、予備校の場合、通学での費用相場は22万前後、通信では20万ほどが相場になります 。
気になったところの資料を請求し、比較検討してみることをおすすめします。
まとめ
社労士試験は8科目と細かい科目に分かれている試験です。
なおかつ各科目に足切りラインが設定されているため、全科目をまんべんなく勉強する必要があります。
そうした細かい勉強を効率的に行うために、やはり独学ではなく予備校の受講をおすすめします。
最新の制度改正にも対応した勉強をする必要があります。
最新の情報に関しフォローもしてくれる、予備校に通うのが合格への近道といえるでしょう。
社労士は近年ダブルライセンスとしても需要が高まっている資格です。
興味がある人はぜひ挑戦してみてください。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ