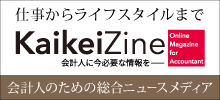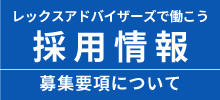転職お役立ち情報

自身で会社や事務所を立ち上げようと考える人は多いでしょう。
会計事務所業務の経験者や会計関連の資格保有者などは、会計事務所の設立を考えることがあります。
しかし会計事務所の設立は一般企業や事務所の設立とは異なる部分が多いです。
会計事務所としての仕組みや法律などのルールにより、会計事務所の設立では一般企業などとはまた違ったものが求められます。
この記事では、会計事務所を設立するまでの手順などを解説します。
会計事務所の設立に至る理由や一般企業などの設立との違いについても取り上げました。
会計事務所の設立に至る理由
まずは会計事務所の設立に至る主な理由を紹介します。
どのような理由から会計事務所が設立されるのかを知ることで、設立に対するイメージがより明確となるでしょう。
かねてから独立開業が夢だったから
独立して会計事務所を設立した人には、かねてから将来的に独立したいと考えていた人が多くいます。
このような人は会計事務所で意欲的に業務を進め、必要な経験を十分に積んだと判断した段階で独立します。
独立という目標を達成するため計画的に行動する人が多いです。
独立までの期間は人によって異なりますが、いずれにしろ夢を叶えることを優先的に進めています。
今いる事務所が閉鎖となったものの転職に前向きでもないから
それほど強い独立志向は持っていなかったものの、状況に合わせて独立したという場合もあります。
特に多いのが、勤めていた会計事務所の閉鎖をキッカケに独立するケースです。
勤め先の会計事務所が閉鎖となったものの、これまでの職場が居心地良かった・長く勤めてきたなどの理由から転職活動に対して前向きになれないケースもあります。
このような場合は会計事務所業務を続けるために、独立という手段をとることが多いです。
自身のやりたいことに対する方向性が明確だから
もとは独立志向を持っていなかったものの、働いていくうちにやりたいことの方向性が明確になったため独立し事務所を設立するというケースもあります。
理想を実現したい気持ちが強い人に多いです。
会計事務所で勤務しているうちに、より理想的な会計事務所についてのイメージが湧くことがあります。
実現可能性もしくは意欲が強いものの、今の会計事務所を変えることや理想的な会計事務所へ転職できるとは限りません。
結果として独立し自身で会計事務所を設立することになります。
希望の条件を妥協しない!今の働き方を変えたい
税理士・税理士科目合格者向け
転職相談会
会計事務所設立の手順
続いては会計事務所設立の手順を紹介します。
一般企業の設立とは異なる部分があるため、事前に確認が必要です。
公認会計士または税理士として登録
大前提として、公認会計士または税理士に登録する必要があります。
試験合格や実務経験など要件を満たし、申請手続きが通れば資格保有者となります。
ただし実際には資格取得直後に会計事務所を設立するケースは多くありません。
資格取得してからすぐだと、会計事務所で経験を積んできたとはいえ、あくまで資格を持たない状態での業務です。
そのためしばらくの間は会計事務所で所属税理士として働くケースがよく見られます。
開業資金を貯め十分な額になったらオフィス契約や備品購入
会計事務所設立にはまとまった資金が必要です。
所属税理士として経験を積み人脈をつくりながら、開業資金を貯めていきます。
目標金額や設立時期・毎月の貯金額などをなるべく具体的に決めておくのが、順調に開業資金を用意するためのコツです。
- 税理士登録や開業にかかる資金例は以下のとおりです。
- 税理士登録費用
- 税理士会会費
- オフィス契約料・家賃
- オフィス家具代
- 会計ソフト・税務ソフト代
- 広告費・マーケティング費
開業資金が十分に貯まったらいよいよ事務所設立の具体的な準備に入ります。
オフィスの契約や備品購入など、運営を進められるよう準備を進めていきます。
会計事務所として運営できる体制が整ったらなるべく早めに業務が開始できるよう、計画的かつスピーディーに動くことが大切です。
必要書類の準備・登記・届出
一般の会社設立と同様に、会計事務所設立の際にもさまざまな書類が求められます。
税理士登録はすでに済んでいる状態の場合、税理士会へ以下の書類が必要です。
- 変更登録申請書
- 変更登録申請に関する届出書 (第26号様式)
- 税理士事務所設置同意書
- 事務所間取り図
会計事務所に勤務する所属税理士が開業税理士になる場合、税理士会の登録情報を変更する必要があります。
それが上2つの書類です。会計事務所の設置に関する書類も求められます。
紹介した以外にもケースによっては、「税理士事務所設置に関する誓約書」「登記事項証明書」「賃貸借契約書」が必要とされることもあります。
必要書類は税理士会によって異なるケースがありますので、事前に開業を考えているエリアの税理士会で確認しましょう。
書類の用意や提出をしながら、登記および届出を進めます。
これらがすべて済めば、無事に会計事務所設立の完了です。
求人情報はこちら
一般の会社設立と会計事務所設立の違い
一般の会社設立と会計事務所設立にはいくつかの違いが見られます。
これらを紹介します。
用意する書類
先述したように、会計事務所設立のためには税務署だけでなく税理士会への書類提出も必要です。
そのため一般の会社や個人事務所に比べて書類の用意が煩雑で時間がかかります。
開業届や青色申告承認申請書などは、開業してから1ヶ月以内の提出が求められます。
しかしそもそも会計事務所設立のためには税理士会での手続きを完了させなければいけません。
税理士会へ申請に必要な書類を提出してからおよそ1ヶ月かかるため、余裕を持った手続きが必要です。
日税連への届出
個人事務所ではなく法人を設立するのであれば、会計事務所も一般企業と同様に法務局での登記申請をおこないます。
それに加えて会計事務所が税理士法人となる場合には、日本税理士会連合会(以下:日税連)への届出も必要です。
個人事務所としての運営であれば所属エリアの税理士会での手続きのみで済みますが、将来的に税理士法人として規模を拡大することもあるでしょう。
この場合は税理士会の上部機関である日税連へ届出をおこなわないと、実際の業務を進めることが認められません。
個人事務所から法人成りする場合においても、一般の個人事務所と会計事務所では違いが見られます。
運営形態そのものが大きく異なる
会計事務所は運営形態そのものが大きく異なります。
前述したように、会計事務所は有資格者のみが運営できるということで、設立後も税理士会への会費支払や必要に応じた更新手続きなどをしなければなりません。
一般の個人事務所よりも手続きが多いといえます。
また会計事務所は同エリア内において複数運営されているケースがほとんどです。
そのためライバルがいるのが当たり前という環境であり、一般の個人事務所以上に地域での営業や経営戦略が求められる可能性が高いです。
会計事務所を設立して税理士として独立すれば、所属税理士以上の年収を見込めるケースが多いでしょう。
しかし運営を続けるための手続きの多さや難易度の高さなど、注意が必要な部分もあります。
求人情報はこちら
まとめ
会計事務所の設立には、一般企業や事務所の設立以外にもさまざまな書類や手続きが求められます。
税理士法などのルールに基づいたものであるため、会計事務所を運営するためには必ず守らなければなりません。
手間が多いと感じるかもしれませんが、会計事務所を設立して独立することには所属税理士では得られないメリットが多数あります。
もし独立への意欲や、理想的な会計事務所や働き方を実現させたいという気持ちが強いのであれば、自身で会計事務所を設立するのもひとつの手段です。
会計事務所を設立するのであれば、ぜひ今回紹介したようなポイントを押さえてください。
Profile レックスアドバイザーズ
公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ